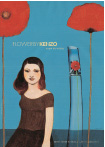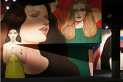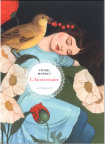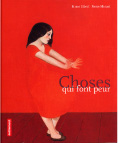-

人間の骨格、筋肉はほぼ同じ比例で、一定の仕組みがあります。この絵の、ごく小さな部分をアップしました。腕部、手首部、手のひら部、指部のそれぞれの骨の構造と役割が省略されていますが、表現されています。枝を後ろ手で握っています。腕部が垂直に下り、手首部でほぼ直角に手前に曲がり、手のひら部が枝に載り体重を支え、そして指が枝の下へと巻き込まれる。小さな絵でも、しっかりした観察と表現がされています。絵の基礎としての安心感をもたらし、その上で、絵の持つ神秘に酔うことになります。基礎力のある絵ですね。
-

彼の作品は、日本的と言われるし、私もそう思います。また、そこが今的で注目されるところでしょう。では、それはどこから来るか?そのひとつが、西洋画の遠近法を採用していないところ。平面的で装飾性に富んでいます。日本画に近いのかな・・・。例えば、手前の果物がこの位置に置かれた場合、遠近法視点で見ると顔は奥行きをもって描かれるでしょう。とくに光の入り方が一定ではありません。まさに作者の想像に浮かぶものをコラージュしています。それぞれは立体感のあるように描かれていますが、その構成が2次元でなされている、その辺が不思議さと新鮮さを与えるのでしょう。
-

甘美で神秘、そして強い物語を感じさせる優れた作品です。少し恐ろしさも。それは鳥が肌をつつくことに起因しているのでしょう。が、深い要因は、画面構成にあると思われます。画面を二分する水平線が、大きく傾き、非常に不安定。次に色。髪の毛の黒が、不安が流れ出るように広がります。ちょっと濁ったブルー。画面を構成する重要な要素にミステリアスな仕掛けがされているのです。絵を描く技法は高度な上に、色と形で物語を生み出す能力は、さすが世界が認めるところですね。
-

顔のまわりに、くっきりと輪郭線が引かれています。おおよそゴッホ以前は、西洋画には輪郭線の概念はありませんでした。顎の前に出たところを光が当たる部分とし、数センチへこんだ首を影として暗くし、立体感を付けていました。「顔には凹凸はあるが輪郭線はない」というのが、西洋画の考え方でした。 が、日本の浮世絵を見たゴッホ時代の画家たちが『線』を発見し多用するようになりました。モルネの絵は、頬は光と影で表現し、際立たせるために、輪郭線を使っているようです。
-

アップのものは約3×3cm部分の拡大です。非常に小さな部分まで、精密にていねいに描かれています。凹凸のないふっくらとした、平面的な顔を描く彼にとって、目は絵の成功を左右する重要なパーツ。ですから、明るい部分から暗く落ち込む部分まで、なめらかなブラデーションを作っています。そして際立たせるところに細い筆でしっかりした色を入れます。皮膚の肉の盛り上がりはあるものの、日本の美人画に近いような手法が取り入れられています。
![]()